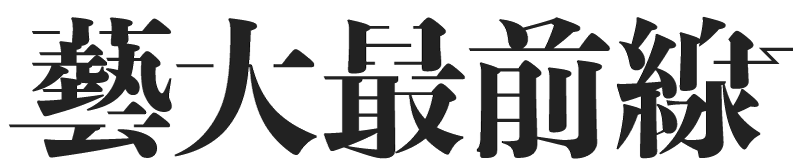「童心に帰って自由な発想を引き出された」
藝大と花王〈前編〉
藝大最前線は、本学の取り組みを紹介しながら、本学と社会との繋がりや、アートの可能性を伝えていく新コンテンツです。 第一回は、企業と大学との取り組みについて、花王と藝大がこれまでに行ってきたコラボレーションを振り返りつつ、アートシンキングによって揺り動かされる、花王社内の変革に迫ります。 前編は国谷裕子理事による花王社員及び藝大教員へのインタビュー。後編は花王を牽引する長谷部佳宏社長と本学の日比野克彦学長による対談です。
【はじめに】
「アートって社会の役に立つの?」
これは藝大が社会から向けられている純粋なクエスチョンでもあります。そもそも藝大は社会とどんな風につながっていこうとしているのでしょう。一体どのような形で社会の役に立つことができるのでしょうか。その解答の一つとして、2020年からはじまった花王と藝大の取り組みが挙げられるかもしれません。花王株式会社からの受託事業として行われた本プロジェクトでは、これまでの研修所を再創造すべく、花王の新たな施設である新佑啓塾の構想をめぐって、アートシンキング(=芸術思考)をもとに花王社員自らが設計に関わるワークショップが行われました。ワークショップでは、建築に向けたものだけにとどまらず、「まず描いてみよう、つくることから始めよう」という、いずれも藝大の授業で行っている実践から始めるというスタンスが共有されています。また2021年には、新佑啓塾プロジェクトの発展形として「花王ミュージアムRebornプロジェクト」が実現。前回同様にアートシンキングのワークショップを交えながら、現代における花王の情報発信をする施設、空間を構想する内容となりました。一連のコラボレーションを終えた今、プロジェクトマネージャーを務めた花王の石倉康寛さん(執行役員 中期経営戦略部門統括)、藝大教員の清水泰博さん(藝大理事、美術学部デザイン科 教授)、松下計さん(藝大美術学部デザイン科 教授)に、それぞれの立場からプロジェクトを語ってもらいました。
聞き手:国谷裕子(東京藝術大学理事)
花王社員も藝大生も、一緒になってやりましょう
「まったく違う視点からアイデアをいただきたい、というのがスタートだったんです」
そう口を開いたのは花王の石倉さん。新佑啓塾構想のプロジェクトを始めるにあたって、どのような期待があったのでしょうか。
「2020年からコロナ禍に入り、働き方や研修のあり方が刻々と変わっていくなかで、新しい働き方の答えのようなものはまだ誰も見つけられていませんでした。同時に『今の世の中だからこそ、こんな場所が欲しい』という声が社内から出てきはじめたタイミングでもあり、新しく施設を設計するなら自分たちで考えて、自分たちが本当に欲しい場所をつくったほうがいいだろうと思ったんです。ゼロからイチをつくるところはアーティストが得意とするところであり、藝大さんの力を借りてみようと、協働の提案をさせて頂きました」
清水さんは当時をこう振り返ります。
「はじめに花王さんに依頼をされた時は建築の設計へのアドバイスのようなお話だったのですが、そこで興味のある藝大の先生方に集まっていただいて、現佑啓塾を見に行きました。当時の佑啓塾の印象はとにかく豪華、でも使われている感じがしない。建築のつくり方もいつもはゼネコンに少しお任せしているような印象で、その時の計画自体が少し観念的な計画になってしまっているなと思ったんです。もう少し自分ごととして考える必要があるんじゃないですか、ということをお話しして、社員の方たちと藝大生が一緒になってやるワークショップ形式がいいだろうと考えました。そのあたりの実践は松下先生がよくなさっていたので、私と2人でプロジェクトを始めることになりました」
松下さんもそれに続きます。
「僕は普段、デザイナーとして仕事をしています。若い頃は『お金あげるから好きにやっていいよ』と言ってくれるクライアントが良いクライアントだと思っていたんですけれど、どうやらそうではないらしいというのが段々とわかってきました。仕事を進めるうえで、アートディレクションや発想の半分は企業の内部で一緒に考える、スタッフ意識を共有してつくっていく。そのほうが後々しなやかで、デザイナーが離れた後も自分たちで手を入れて修正していける。そういうデザインのほうがよほど機能的だと思うようになったんです。そのプロセスを大学という場所を使ってやっていこうと考えたのがはじまりですね」
大学として社会や企業と繋がりを深めていくと同時に、プロジェクトに参加する学生に価値が流れていくということを常に大切にしていると松下さんは言います。企業との連携によって藝大生が得られるものについても語ってくれました。
「藝大は演奏家とクリエイターが大半を占めているので、自分たちが社会的にどういう位置にいるかということがあまりわからないんですよね。マッピングができない。だから異なった団体の人たちと接することで、『自分たちってこういうことを期待されているんだ』ということに気がつく。自分たちがやらなきゃいけないこともわかってくる。そういうチャンスでもありましたね」
藝大が引き出す、花王のなかに眠る感性
このワークショップでは、「絵を描くこと」「絵を使ったブレスト」「立体モデルをつくること」「手でつくりながら考えること」「繋がりから考えること」「イメージを描くこと」からなる6回のアートワークが行われました。
(1日目の課題「パプリカを描く」より。写真:中戸川史明)
花王の社員の方々には5つの班に分かれてもらい、それぞれの班には藝大生が一人ずつ入ります。まず会場に配られたパプリカを鉛筆を使って描いてみましょう、というところから始まり、花王の製品を材料に妄想しながらインテリア空間をつくってみたり、全身を使って泥で絵を描いたりと、子供に立ちかえったような気持ちで時間が過ぎていきました。全7日間にわたるワークショップを経て、意外な気づきがあったと石倉さんは言います。
「最初は、ワークショップを通して藝大の皆さんの感性や発想をお借りするようなイメージなのかなと思っていたのですが、いざ参加してみるとそうではなくて。むしろ自分たちが普段、無意識のうちに蓋をしてしまっていた自由な発想を引き出していただいたような感覚でした。実は花王のメンバーもみんな感性的な思考を持っていて、ワークショップの過程で童心に帰って思い出すことができた。その体験が今の仕事にも生きているように感じます」
花王のメンバーは真面目すぎる、と言われることが多々あるという石倉さん。その声は国民的なメーカーとして揺るぎのない評価であると同時に、次なるステップへの課題でもあるようです。ですから、最良の一本道をえり抜いていくといった、これまでの勤勉なスタンスを一度取り払ってみる。絵を描いて、体を動かすことで真面目な部分からはみ出してみる。変革のためのきっかけが、ワークショップのなかに隠されているといいます。
「石倉さんにお聞きした話のなかで僕がいちばん興味を持ったのは花王の『アングラ活動』というものです」と、清水さんは話します。昔から花王には、通常業務が終わった後に研究員同士が雑談をしたり、いろいろなことを実験?構想したりする文化がありました。まるで部活のような集い、そういう仕事後の活動のなかから新たなアイデアが生まれることもあったといいます。その文化が少しずつ薄れてきており、コロナ禍もあって難しくなってきているのではないかという石倉さんの懸念も聞きました。もしかすると、今花王に必要なのは「部室」なのかもしれないと思いました。学校の授業外で自由な活動をしているクラブ活動のような。
「この施設は出島みたいに社外に突き出したスペースになってもいいですね。仕事が終わってここへ来たら好きにしていいよ、という風な。そこには周辺地域との繋がりもあると思うんです」と清水さん。花王に必要な施設のあり方が、対話を通じて徐々にクリアになっていきます。
(本プロジェクトの舞台である佑啓塾。取材は改築前の佑啓塾で行われました。)
勘でつくる藝大生。ファーストスケッチにヒントがある
ワークショップを設計するうえで、松下さんには参考にした考え方があるといいます。それが、イタリアのデザイナー、ブルーノ?ムナーリの〈3つの切り口〉。そのうちの一つが〈物事をひっくり返して考えよう〉というもの。
「都市を考えるのなら地方を、生を考えるなら死をセットにして一緒に視野に入れようということですね。たとえば、清潔な花王について考えるために、あえて『不潔な花王』をイメージしてみる。その発想を絵に描いてアイデアをポジティブな方向へ広げていく。そのようなメソッドを今回のワークショップへ組み込んでみようと考えました」
2021年に行われた「花王ミュージアムRebornプロジェクト」では、実際にこの発想法を取り入れたワークショップを行い、花王メンバーと藝大生が一緒になって新たなミュージアムを考えました。藝大生が絵を描くスピードに石倉さんは驚いたといいます。
「たとえばカフェの話をしていたら、横でささっとスケッチを描いて『こんな感じですね』という風にみせてくれるんですよ。最後のプレゼンテーションでは3枚しか使わないのに、サラサラと30枚以上の絵を描くんです。その集積をまったく苦にせずに生み出す姿勢を、私たちは仕事のなかで忘れているなと。30枚のうち、一見ムダ打ちのようにみえる27枚のスケッチから、後になってアイデアが得られることもある。そういうことに気付かされたんです。リアルな現場で時間を共にしたので、本を読んだり、レクチャーを受けたりするのとはまったく違うレベルで体感することができました。ワークショップを終えてからもうしばらく経っていますが、私はいまだにその藝大生から学んだ姿勢を忘れずにやっています。効率だけではない別の道があるんだなと」
石倉さんの体験は、まさにアートシンキングの一端かもしれません。アートが社会と関わりを持とうとする時、アーティストの制作プロセスそのものに価値があると松下さんは言います。
「アーティストが作品をつくる時、『何をつくろうか?』と考えながら最初に手をつける部分、つまり真っ白い紙に初めに描きだす制作のプロセスを、僕らは『ファーストスケッチ』と呼んでいます。これはアーティストだけの独占的なものではなくて、みんなが使える部分だと思うんです。小さな絵を描くとそれが小さな現実になって、そこから批評が生まれる。『なんかいいよね』とか『ちょっと違うな』という風に。そこには必ずその人の美学や感性が働いています。人間は本来、感性や美学、あるいは芸術を愛する心みたいなものを全部セットにして成り立っていますから」
一方で、藝大生自身もその思考プロセスに自覚的であるというわけではないといいます。ファーストスケッチに光を当てることや、その目的を示唆することは学生にとっても深い意味を持つようです。
「藝大生は突拍子もない発想をしたりするんです」と清水さんはつづけます。
「どこか勘でつくっているというところがあるんですね。何となくそれを思いついて、その発想がどこで『自身の課題』と繋がるのか本人もよくわかっていなかったりする。彼らに対して『どうしてそうなったの?』と訊いていく。『それは違う』とは言わないのが指導の基本ですね。勘というのは総合判断だと私は考えていますから、『論理的には説明できないけれど、何となくこうなった』というのは正しいんだろうと思っています。だから、とにかくやってみなさいよと。やった後になって、『自分はあの時どうしてこれをしたんだろう』『何に価値があると思ったのだろう』ということをすべて考える。その気づきが後でコンセプトになってしまう場合だってあると思います。勘を解読していくわけですね。このプロセスはデザイン?リフレクションと呼ばれていますが、論理的な思考とは異なるやり方として、藝大生には合っているのかなと思っています。まさにアートシンキングですね」
企業×藝大の先にみる、新たな光
藝大はこれからもっと社会との繋がりを深めていきます。今回、花王との一連のプロジェクトを振り返る対談のなかで、企業と藝大の取り組みが持つ可能性がまた少し具体的に広がったように感じます。
最後に、花王と藝大の今後の展開について話してもらいました。
「この先新しい佑啓塾ができて、建物をどのように使っていくのかということも含めて、ぜひ引き続きご一緒させていただけたらと思っています。私たちにない視点を与えてくださったり、花王メンバーの隠れたマインドを引き出していただけたりするので、その度に『こういうことを藝大さんと一緒にやったら面白いだろうな』というアイデアが次々に出てくるんです。これからも楽しみですね」と石倉さん。それを受けて松下さんも顔をほころばせます。
「これからの社会では、『本人が自分自身で最良の道を選んでいけるように、優しく背中を押すコミュニケーション』が大切になってくる気がしています。そのためには新しい話法と新しい場づくりが必要です。おそらくアートの力が求められると思うんですね」
そういったメッセージの出し方のことを〈ナッジ〉と呼んでいます。松下さんはつづけます。
「今、未来を標榜するためのプロジェクトはたくさんあるんですが、そのほとんどがSFというか、サイバーティックな結果を産むものが多いのですね。もっと暮らしに寄った未来のコミュニケーションを、たとえば花王さんがデザインしていく事にまったく違和感がないのです。生活に密着した花王という企業がやる事に意義があると思うんです。それをみて、『私も参加したい』という学生も出てくるんじゃないかな」
新佑啓塾のプロジェクトを先駆けとして、企業と藝大の関わり方には多くの可能性があると、清水さんも指摘します。
「今回のプロジェクトは主にデザイン科の先生で進めましたが、おそらくいろいろな科でできると思っています。音楽分野も加えるとさらに面白くなってくるはずです。参加する先生方、学生たちによってさまざまなアートシンキングができるのではないかと思います」
藝大が行うアートシンキングが、企業を通じて商品やサービスというかたちで社会へ出ていこうとしています。これまでの価値観ではもはや立ち行かなくなっている世界で、一体何が幸せなのか、何がウェルビーイングなのか、問いかけをつづけながら価値創造をしていくことが求められています。花王と藝大が共に手を動かす本プロジェクトのなかに、未来へのヒントを垣間見たような気がしました。
>> 後編:藝大 日比野克彦 学長 × 花王 長谷部佳宏 社長対談
構成:野本修平 撮影:縣健司