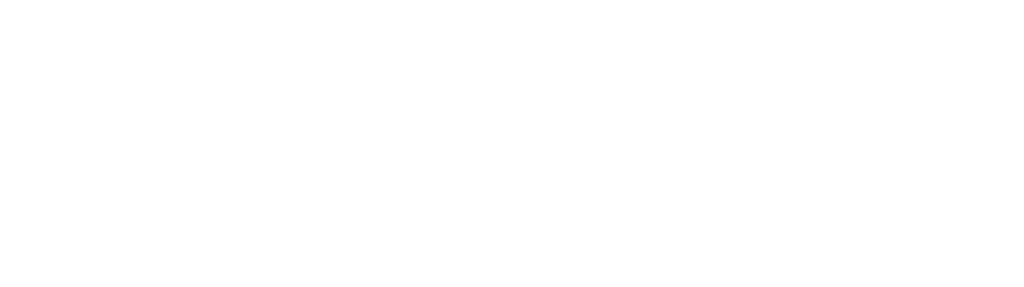- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第六十ニ回 樫村芙実「7日間の探検ー藝大?AAスクール合同ワークショップ」
雲ひとつない快晴が続く2023年の年始、ロンドンのAAスクールから10名の大学院生が藝大建築科にやってきました。遡れば2015年から続くAAスクール?藝大の合同ワークショップは、今年対面での実施を再開し、COVIDによって空間を共有出来なかったことが大きな損失であったことを痛感させられました。藝大の参加者は総勢25名、7日間の彼らの様子からは何か渇望のようなものを感じました。
フィールドワークを行い、見慣れた上野周辺の風景が、都市という巨大で複雑な生き物の片鱗に見えてくる、その発見の過程は通常の設計課題では得難いものです。例えば敷地の一つだった上野検車区は、銀座線を一時留まらせる休憩所のようなもので、その姿は100年の年月を経て上野の町に当たり前に溶け込んでいるけれど、ロンドンからきた学生にはその存在?歴史?動きすべてが興味を掻き立てるので、スケッチ片手に執拗に観察を繰り返しますーさながら虫好きの少年が虫眼鏡片手に草むらを観察するように。これを当前としていた我々の目にも、次第に、線路というネットワークの端が一部だけ街中に顔を出していることの奇怪さや、東京の巨大なインフラが足元深くに渦巻いていることの鼓動のようなものを共有し始めます。

上野周辺地域の観察
また、目的やゴールを明示されない難しさも、魅力です。デザインの提案を前提とする課題とは異なる状況にあって困惑顔の学生たちが、言語や価値観のバリアをかわしながら必死で手を動かし、スケッチや模型で自分の興味を示していきます。議論を理解し、次に何が起きれば良いのかを探っていく。どこに行くか分からないまま未知の場所を探検するような、あるいは最高の波を期待しながら波乗りをするような。探求そのものが目的であり、ここでなくては得られない機会です。
議論の風向きを捉え、先導者が誰かを読み、言語のバリアを超えようと表情を読み、タイミングを見計らう。この波乗りはお互いが同じ空間を共有しなければなし得ません。
そして、7日目の講評会後に残されるのは、やり切ったという充実感とは違い、世界の広さや、目指すべき場所の高さを目の当たりにし、その前に取り残されたかのような、喪失感にも似た不思議な感情です。会が終わっても尽きない学生同士や教員との話の中で、心に残ったモヤモヤを必死に鮮明にしようとしている姿に、学生だった頃の自分の姿を重ね、私自身もその後味を思い出していました。それは不安というよりも、まだ興奮の中で好奇心と探究心を剥き出しにし、まだ何かを求めるような気持ちです。
これから寒さの後に暖かさが来れば、参加した学生たちは各科?各学年の課題に戻ります。この短期間のグループワークで詳らかになった世界の大きさの中で、今度は個人の興味を探求し育てていってくれればと思います。東京で、あるいはロンドンで建築を学ぶ彼らと共に、都市の移り変わりを敏感に感じ取っていけることは、存外の喜びと感じています。

上野検車場チームの発表の様子

浅草寺参道を敷地としたチーム
【プロフィール】
樫村芙実
東京藝術大学 美術学部 建築科 准教授
1983年神奈川県生まれ 2005年東京藝術大学美術学部建築科 卒業 2007年東京藝術大学美術研究科建築専攻 修了 2011年テレインアーキテクツ/TERRAIN architects 設立 主な作品に「TERAKOYA」(ウガンダ、2020年)、「やま仙/Yamasen Japanese Restaurant」(ウガンダ、2018年)、「AU dormitory」(ウガンダ、2015年)、エンダン文庫(インドネシア、2011年)など